
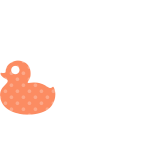
前回のメルマガで、厚生労働省が公表する子ども虐待死の報告書を基礎資料に用い分析した結果として、多胎家庭では単胎家庭と比較して、虐待死の発生頻度が家庭あたりで4~5倍高い可能性があることを報告しました。多胎家庭で虐待死の発生頻度が高いとすれば、その理由は何でしょうか。そこで、今回は多胎家庭における虐待死事例の特徴を分析した結果をご紹介します。詳しくは、Twin Research and Human Genetics誌, 16巻3号, 743-750, 2013に掲載されています。
厚生労働省が公表する「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」(第1次~第8次報告:2003年7月から2011年3月の事例)を集計すると、0歳から17歳までの虐待死事例は総数437児であり、そのうち14の多胎児が含まれていることを前回報告しました。14児の事例について、新聞報道やインターネットなどから複数の情報を収集し、丹念に調べ詳細を確認し、以下の結果を得ました。
14児は全てふたごであり、13家庭に属しています(両児虐待死事例が1件ありました)。生物学的な親(血縁関係にある親)による事例が12例13児であり、両親によるものが3例3児、母親の単独が7例7児、父親の単独が2例3児でした。身体的虐待が10児、ネグレクトが6児でした。身体的虐待とネグレクトが重複していた2児を含みます。4人の母親が10代妊娠だと思われます。また、母親自身が虐待された経験を持っている場合や、精神疾患を有する場合が少なくとも3例ありました。10人中4人の父親には定職がありませんでした。12例中6例で、被虐待児(死亡児)の同胞(兄弟姉妹)のいずれかが虐待を受けていました。その中には、虐待死したふたごのco-twin(ふたごの他方の児)6児全員が含まれていました。ふたご両児が虐待を受けた事例では、家族の機能不全(例えば、養育能力の欠如など)が認められました。ふたごの1児だけが虐待を受けた事例では、1児の障がい、成長・発達の遅れ、愛情の偏りが見られました。この場合に、必ずしも障がいを持つ児の方が虐待を受けていたわけではありません。乳幼児揺さぶられ症候群を思わせる事例が少なくとも1件ありました。海外では、多胎家庭において乳幼児揺さぶられ症候群の事例が多いことが指摘されており、ふたごの泣き時間の長さとの関係で注目されています。
虐待死に至った児の性別、両親の年齢、婚姻状況、母親の精神状態など大部分の項目で単胎児と多胎児の間に差は見られませんでした。調査できた項目の中で、多胎児と単胎児で統計的な差がみられた項目が2つありました。まず、乳児(0歳)死亡事例に占める0か月虐待死の割合です。多胎児では0%(8児中0児)である一方で、単胎児では48%(185児中89児)でした。全体としては、虐待死亡事例を年齢別にみると0歳児が圧倒的に多いことが分かっています。その中でも、特に0か月児(ほぼ新生児期に相当)がその過半に近い割合を占めます。そのような中で、多胎児の場合に0か月事例が少ない(これまで見られていない)理由は今のところ不明です。もしかすると、多胎の場合には出産前後を通じて、医療機関との関わりが大きい点が予防効果をもたらしているのかもしれません。
もう一つは、家庭あたりの児の数です。わかりやすく説明するために家庭あたりの子どもの平均人数で説明すると、1家庭あたりの子どもの数は、多胎家庭で3.2人、単胎家庭で2.2人と推定されました。多胎家庭なのだから子どもの数が多くて当たり前だと思われるかもしれません。しかし、子どもの数が多いこと自体が多胎育児を困難にする、あるいは虐待リスクを高める大きな理由の一つだと言えるわけです。古くより多子家庭(子どもの多い家庭)では、様々な理由で虐待リスクが高いとされています。多胎家庭の場合には、それに加えて同じ年の複数の児を同時に育児するということで、さらなる負担が加わっている可能性があります。
量刑に関しては、13例中12例(15人)についての情報が得られました。全体で4例に執行猶予付きの判決が下されています。この中には、母親単独の7例のうち3例(43%=3/7)が含まれていたことが注目されます。母親の多胎育児の負担を考慮した判決がなされている可能性があるからです。ただし、単胎児例に関しては量刑の情報は得られていませんので、直接比較することができず、この結果だけで断定的なことは言えません。
以上をまとめると、多胎家庭が単胎家庭よりも虐待死事例の発生頻度が高い理由は、多胎家庭に限定されない要因(過度の育児負担、親の養育能力の低さ、一人親、望まない妊娠、10代の妊娠など)と、多胎家庭に固有な要因(ふたご両児に見られる差や両児の比較など)が関係すると思われます。また、量刑に際しても過度の育児負担が加味されている可能性が考えられました。
大木秀一 石川県立看護大学健康科学講座
JAMBA News №36 より