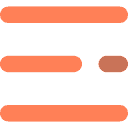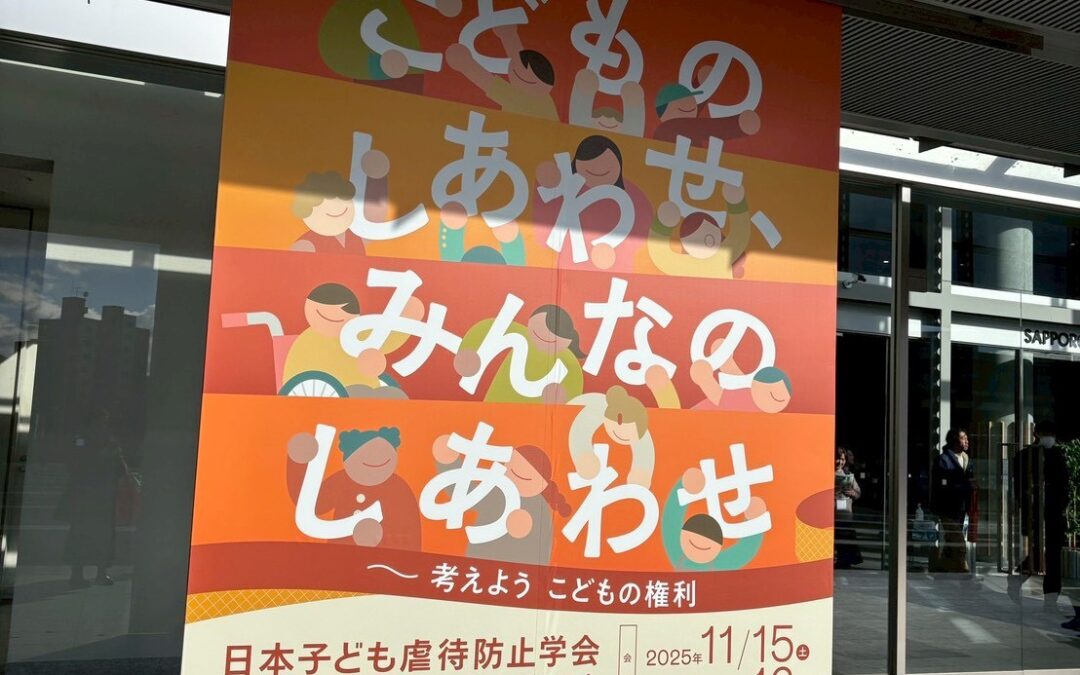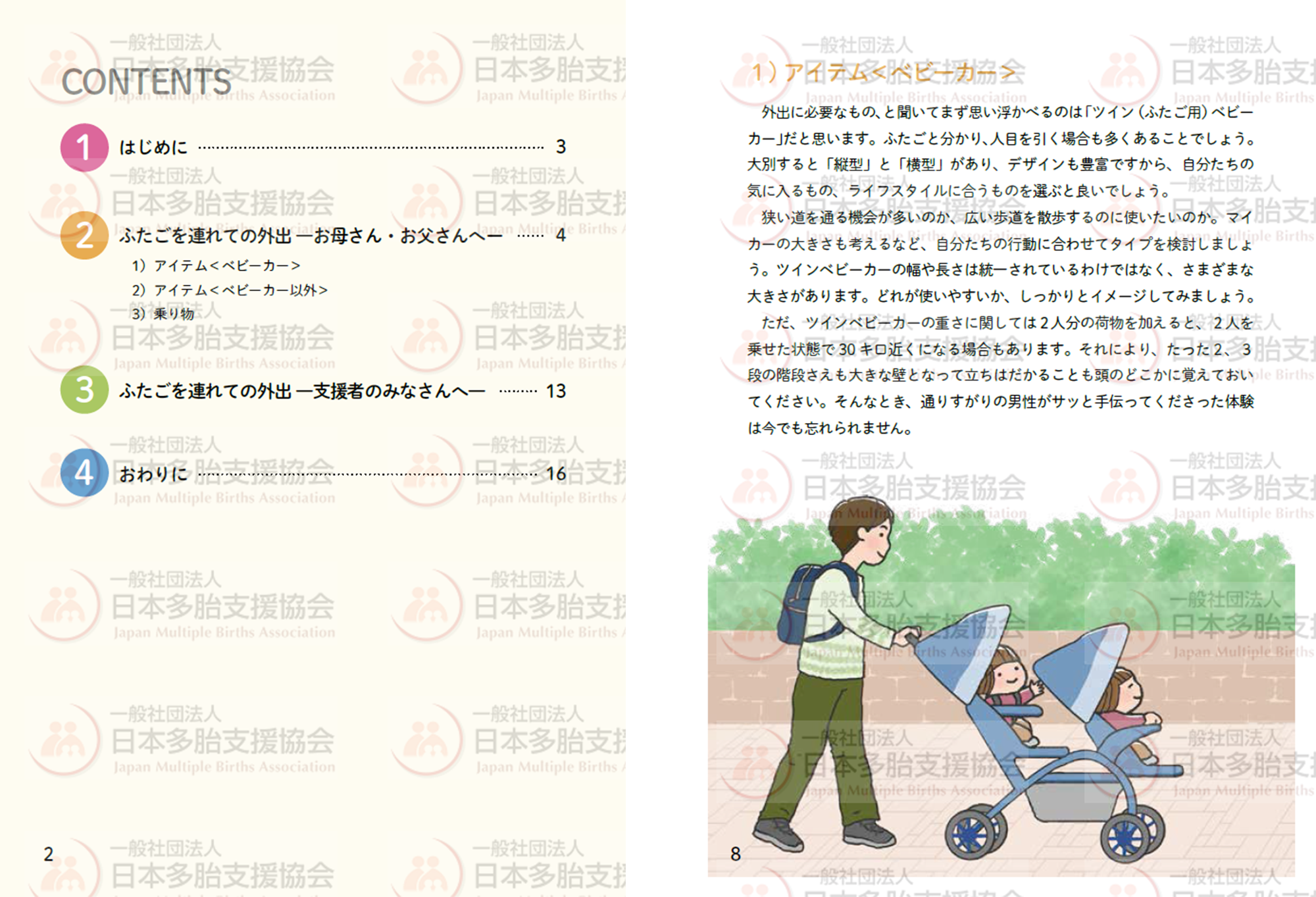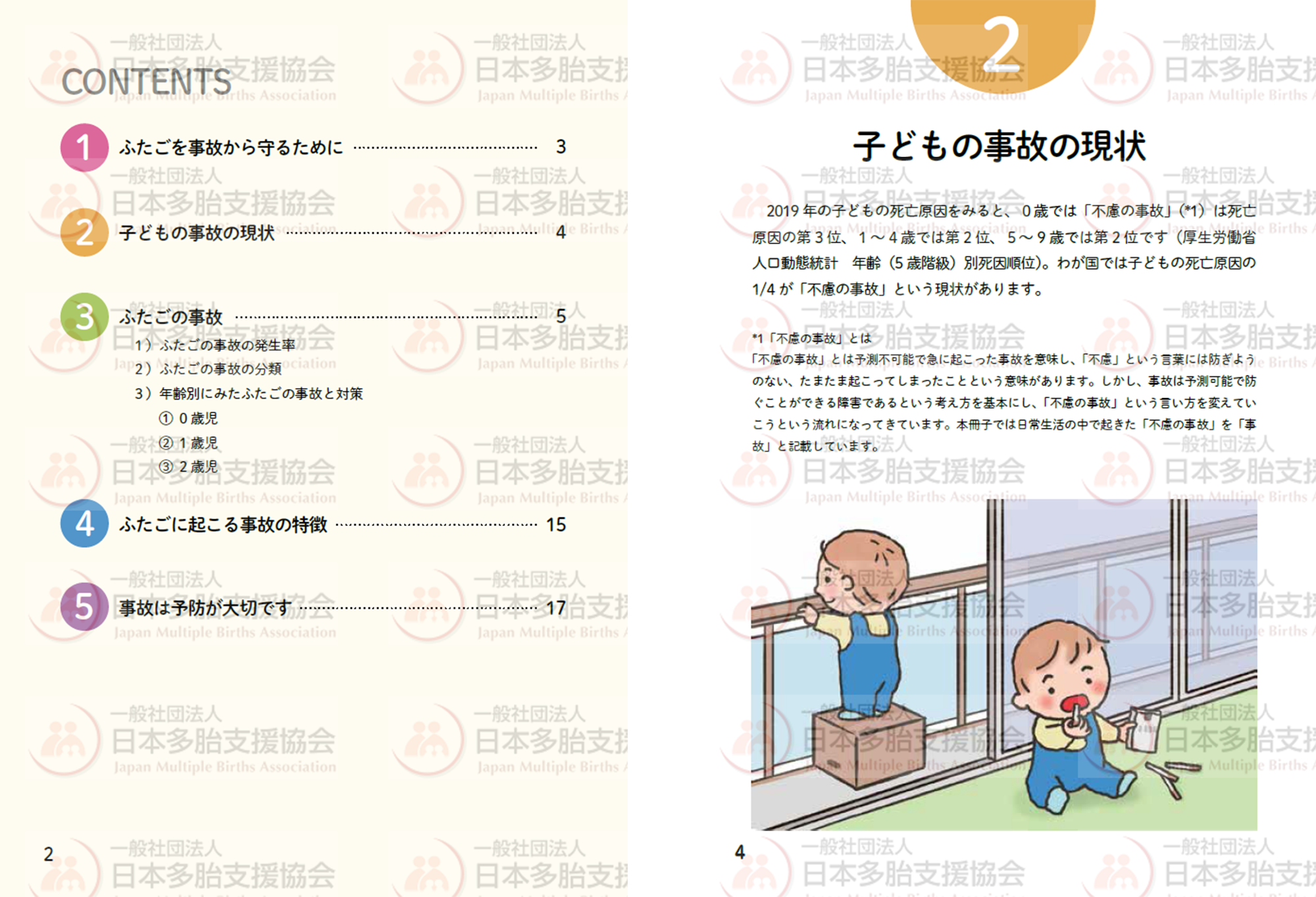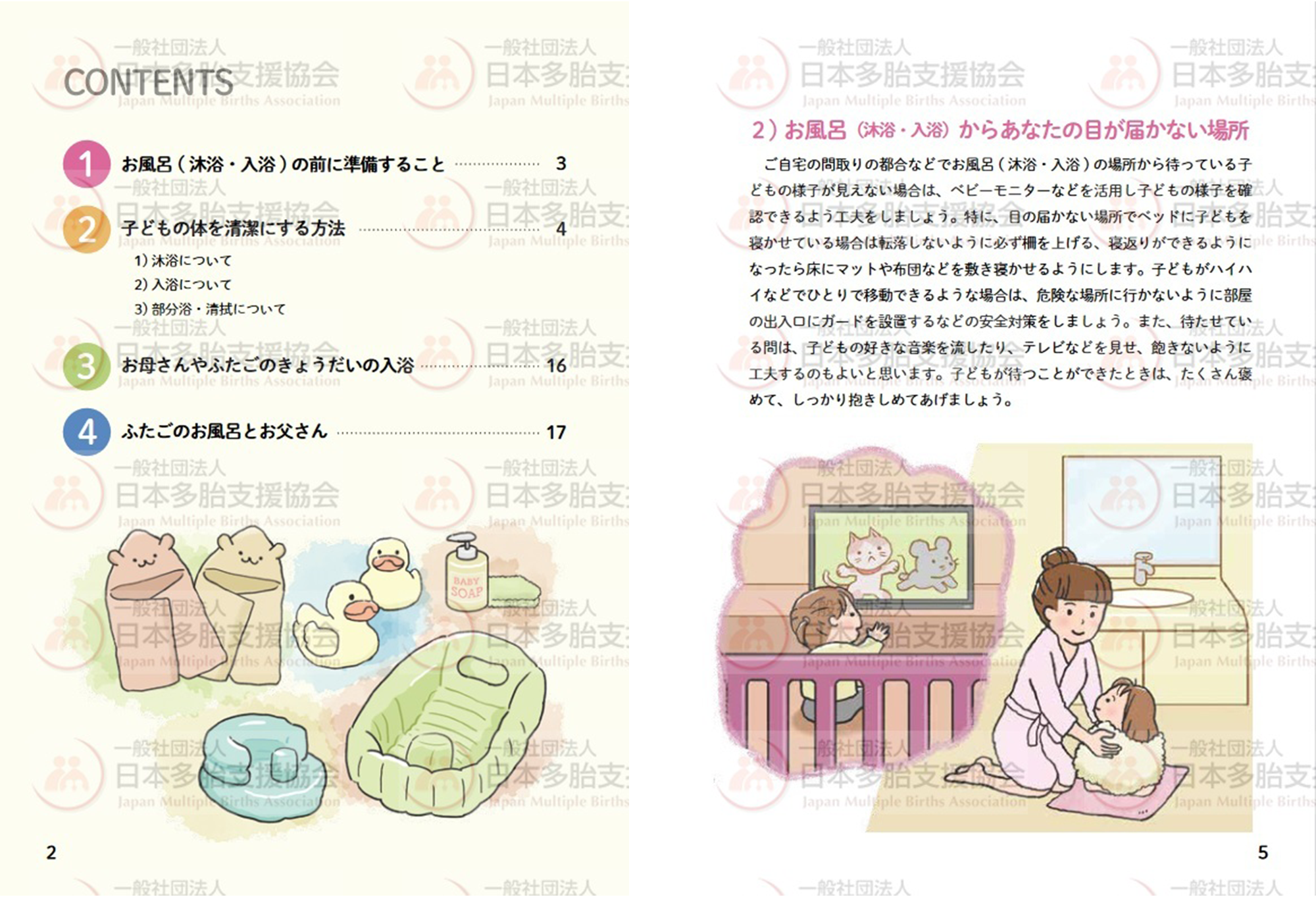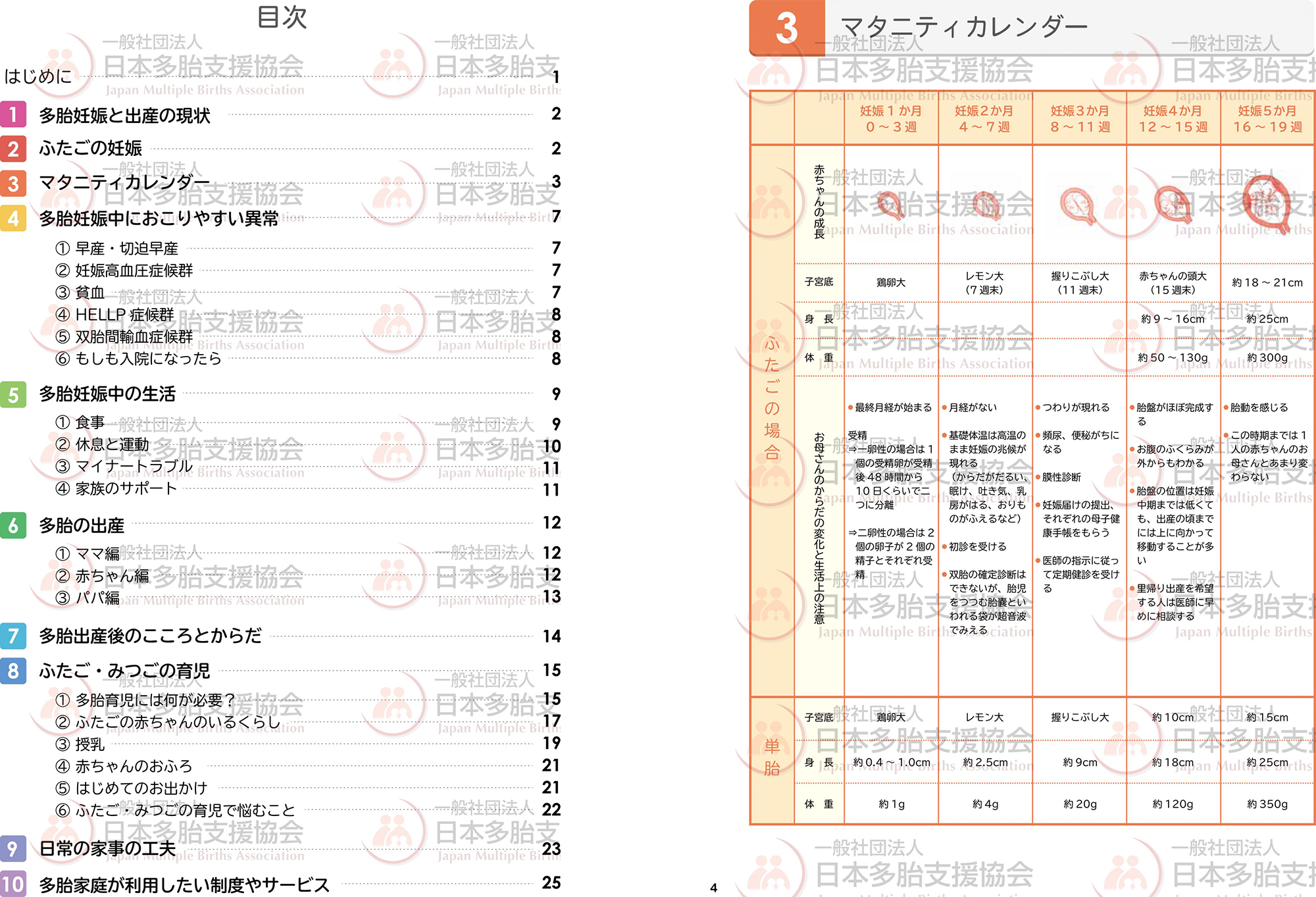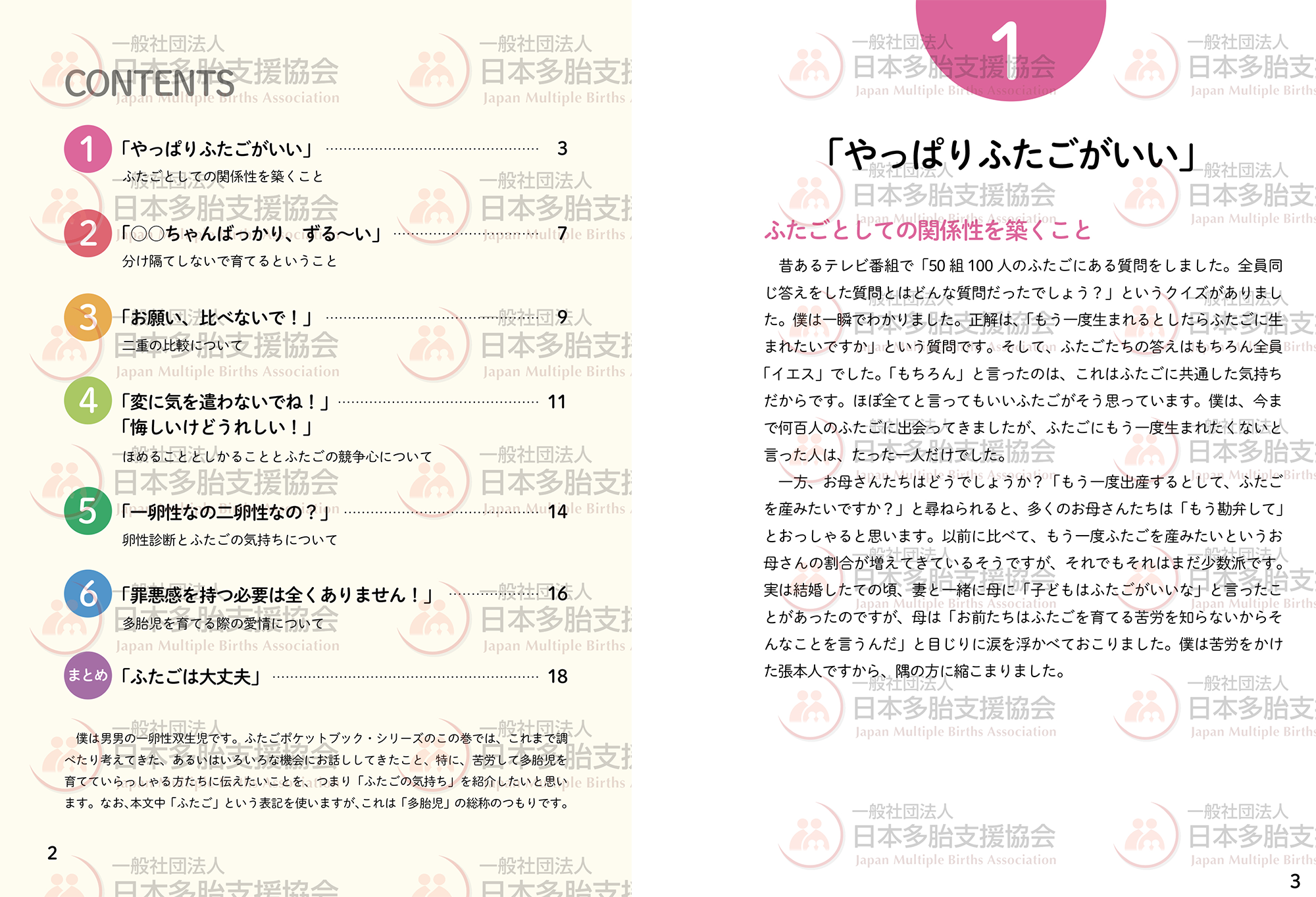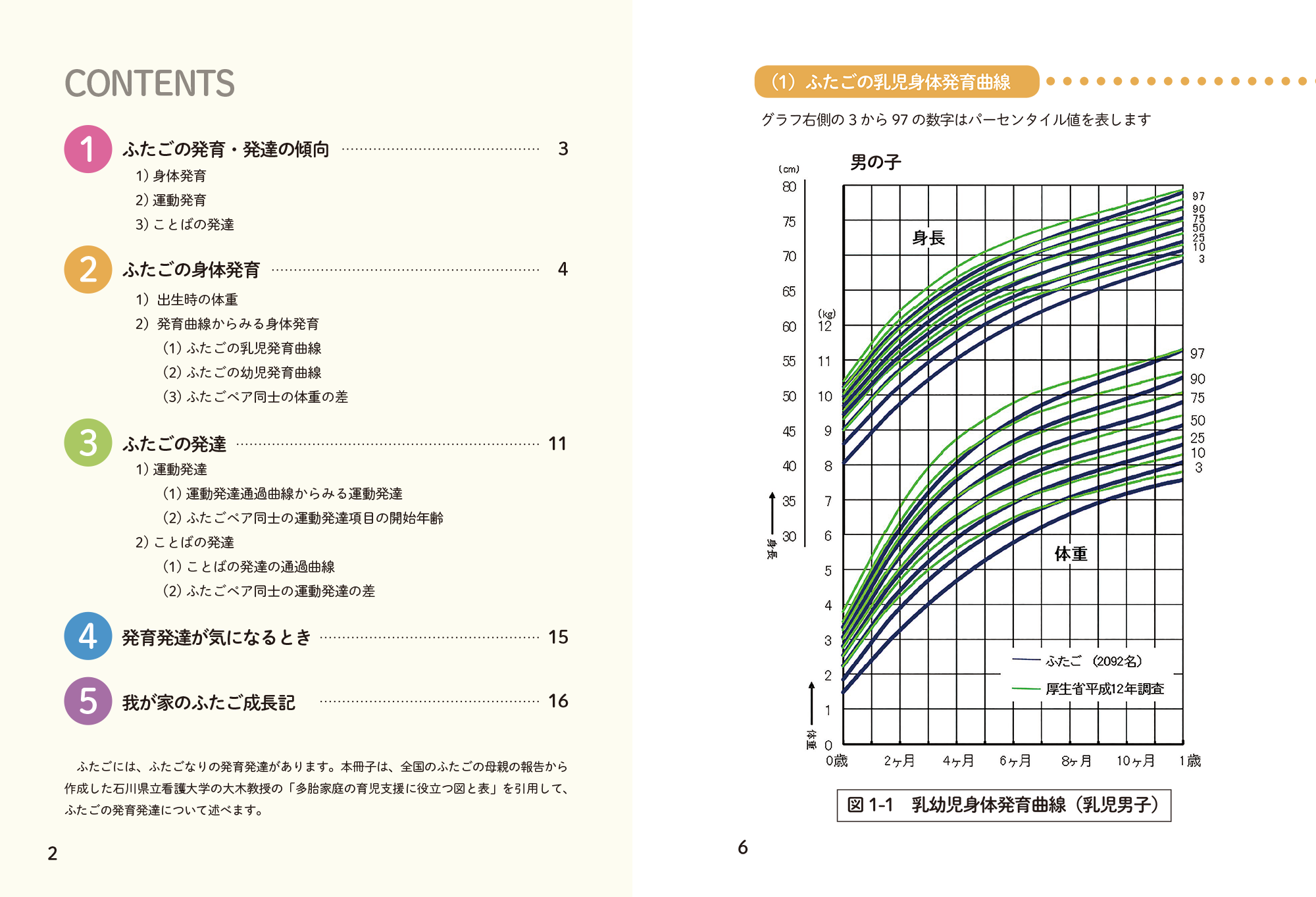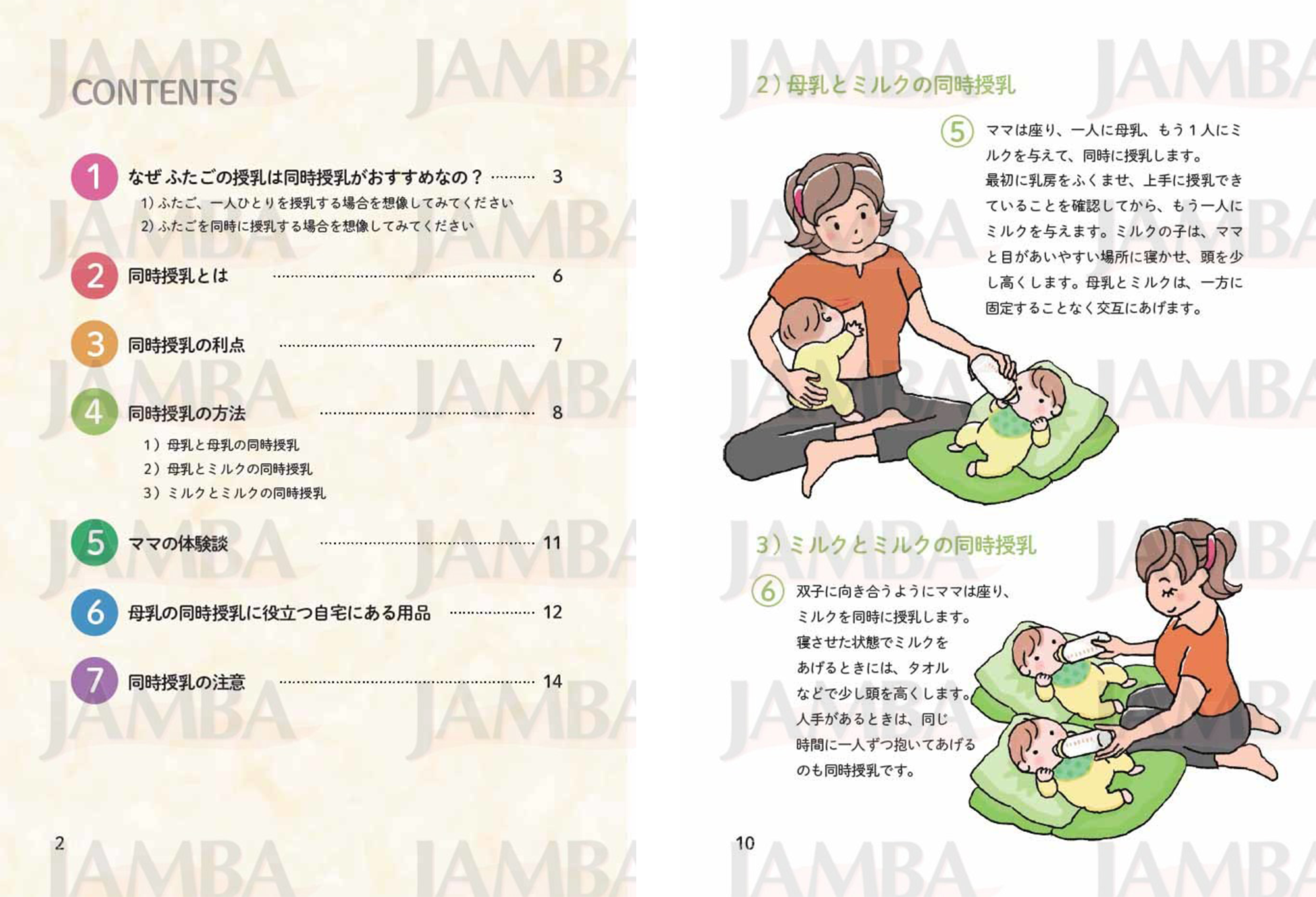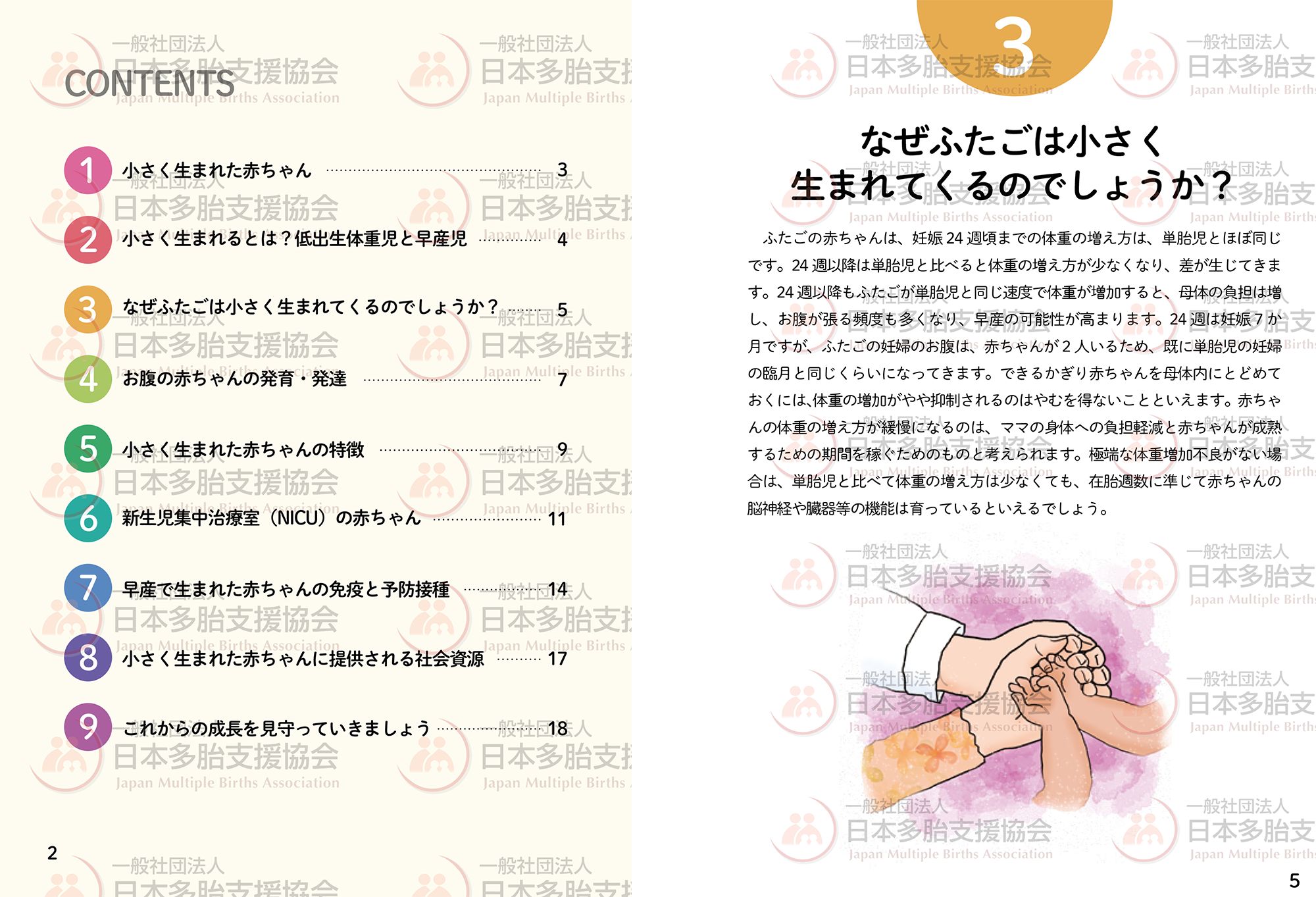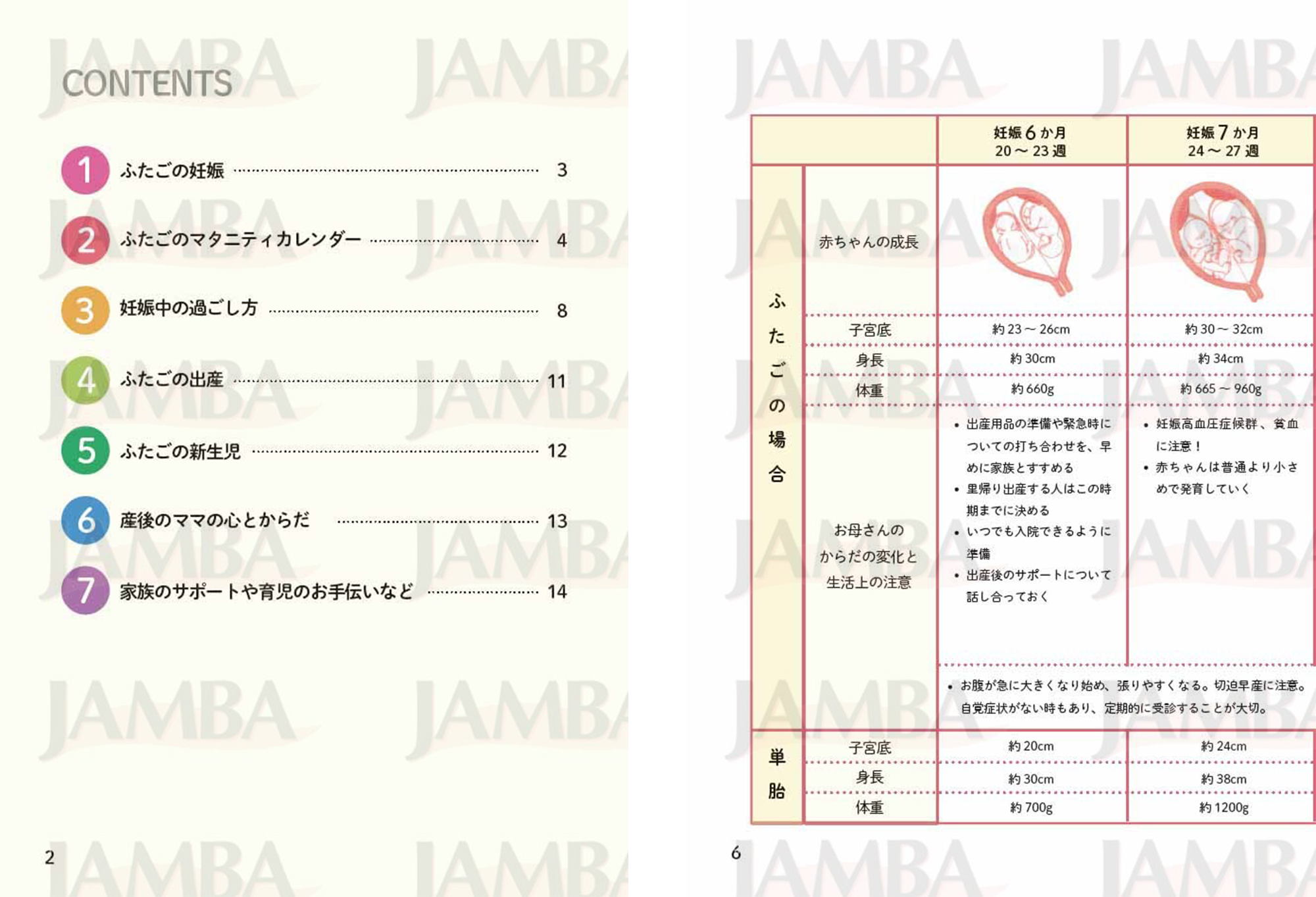2025年11月15〜16日、札幌コンベンションセンターで行われた「第31回日本子ども虐待防止学会」に参加しました。
私たち日本多胎支援協会は、開催日2日目の8:45〜10:25まで、神戸女子大学の服部律子理事を座長として「妊娠期からの虐待防止を目指した多胎家庭支援〜地域を基盤とした多職種連携による支援」をテーマに発表を行いました。
早朝からほぼ満席になるほど多くの方が集まってくださり、多胎支援に対する関心の高さが感じられました。
はじめに服部理事から、このシンポジウムの目的として、多胎家庭はハイリスクで虐待が多いこと、しかし妊娠期から子育てハイリスクになることがわかるため支援計画が立てやすいこと、多職種連携が組みやすいことなどが説明されました。
その後、中原理事から「NPO法人つなげるによるオンラインと対面の良さを活かした多胎支援の取り組み」、松本理事から「三重県での母子生活支援施設におけるレスパイトを目的とした多胎支援の取り組み」、糸井川理事から「NPO法人ぎふ多胎ネットによる多職種連携で虐待防止を図った事例の報告」をしました。
どの取り組みも参加者の方にとっては「そんなことができるのか?!」と目新しく、「オンラインで危険や困難さを感じたケースの場合はその後、どのようにするのか」「秘匿性の高い母子施設でどのように一般の親子が利用できるようになったのか」「病院に入り込んで多胎支援ができるようになった経緯を教えてほしい」など活発に質問がありました。
どの質問も基礎的な質問が多く、多胎家庭の実態については、まだまだ知られていない印象を受けました。多胎支援についての関心は高く、多胎支援は他の支援にも応用が効くことを考えると、今後、ますます多胎家庭の置かれた現状と効果的な支援方法について広く周知していく必要性も感じたシンポジウムでした。