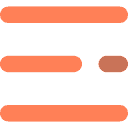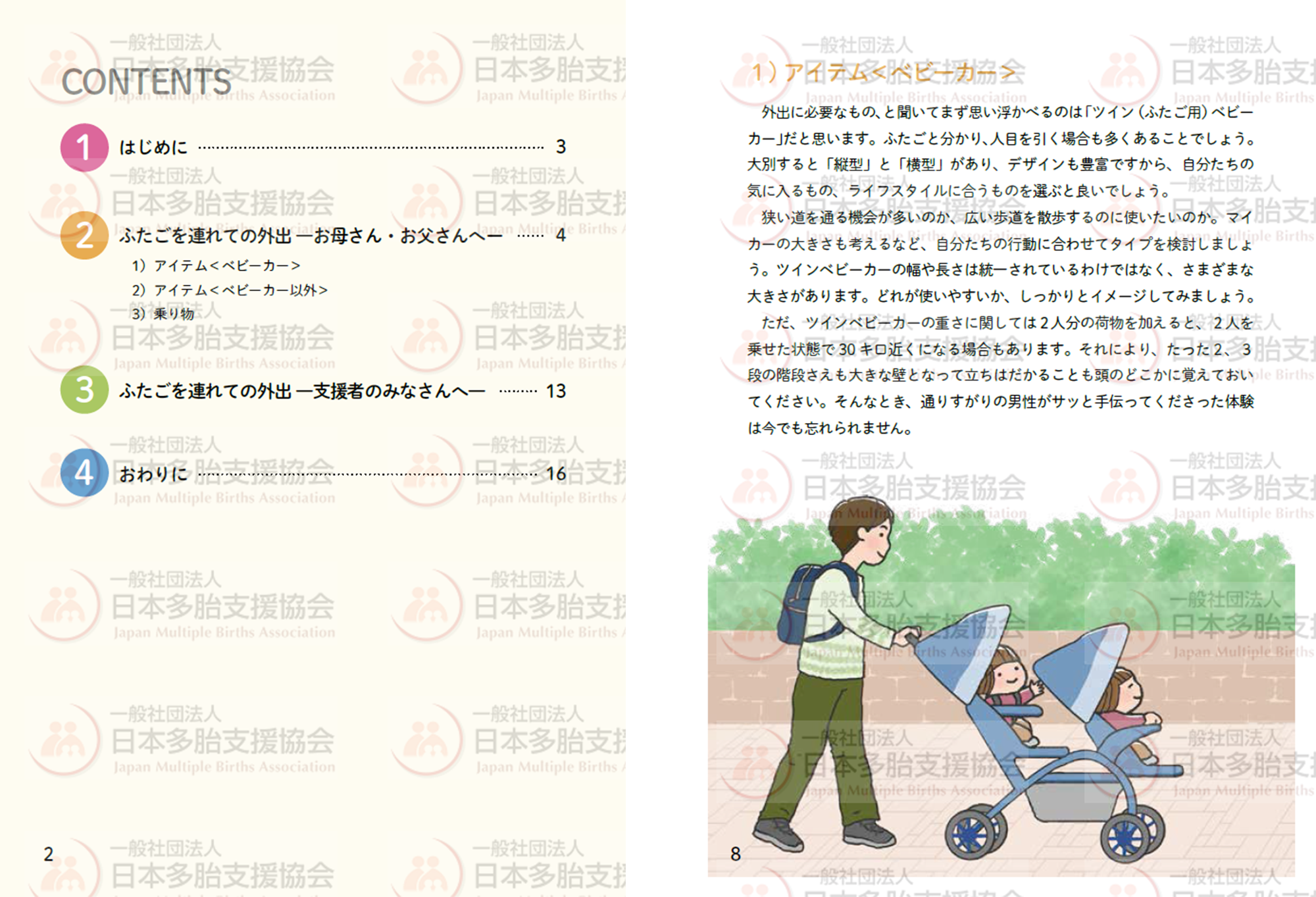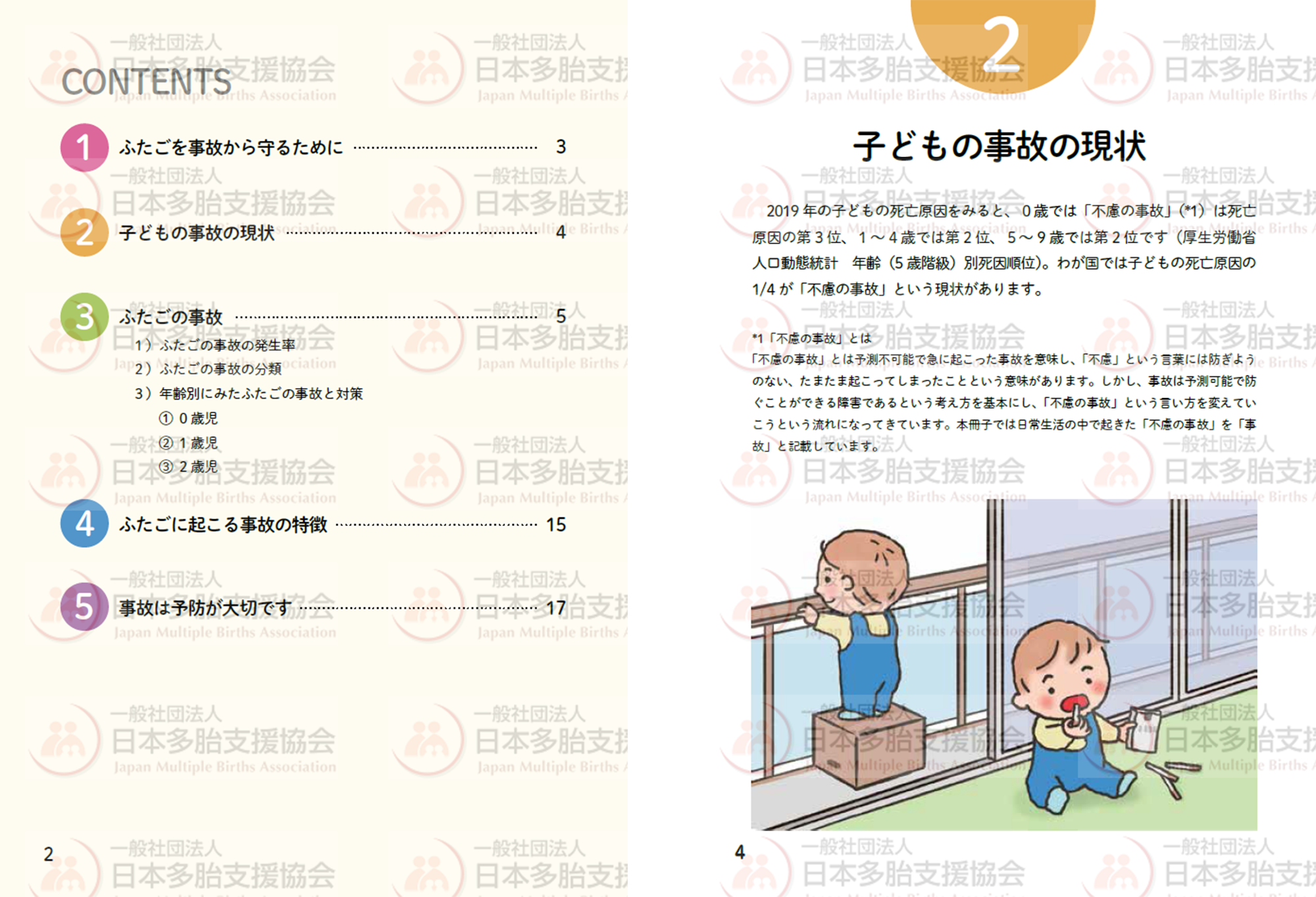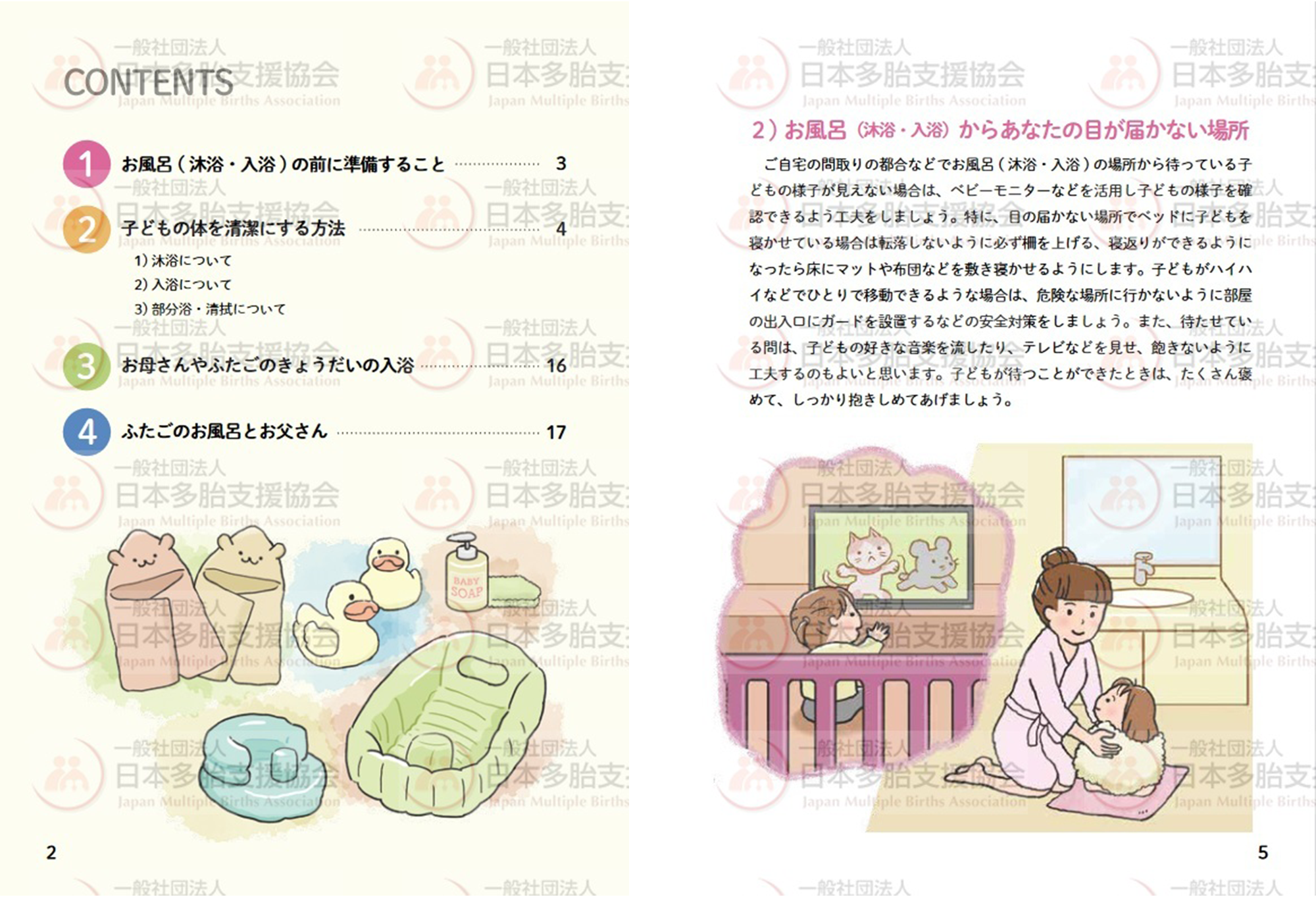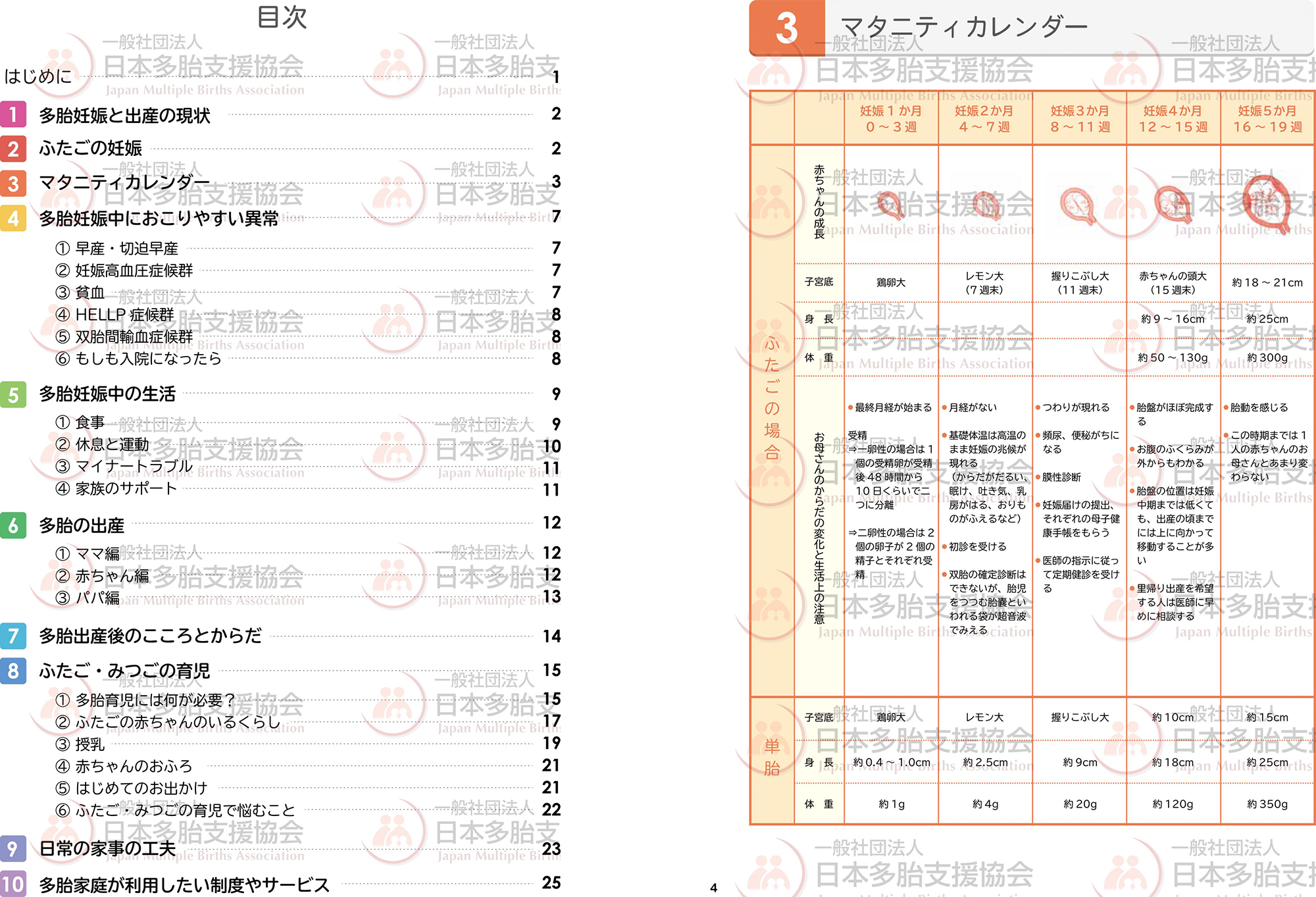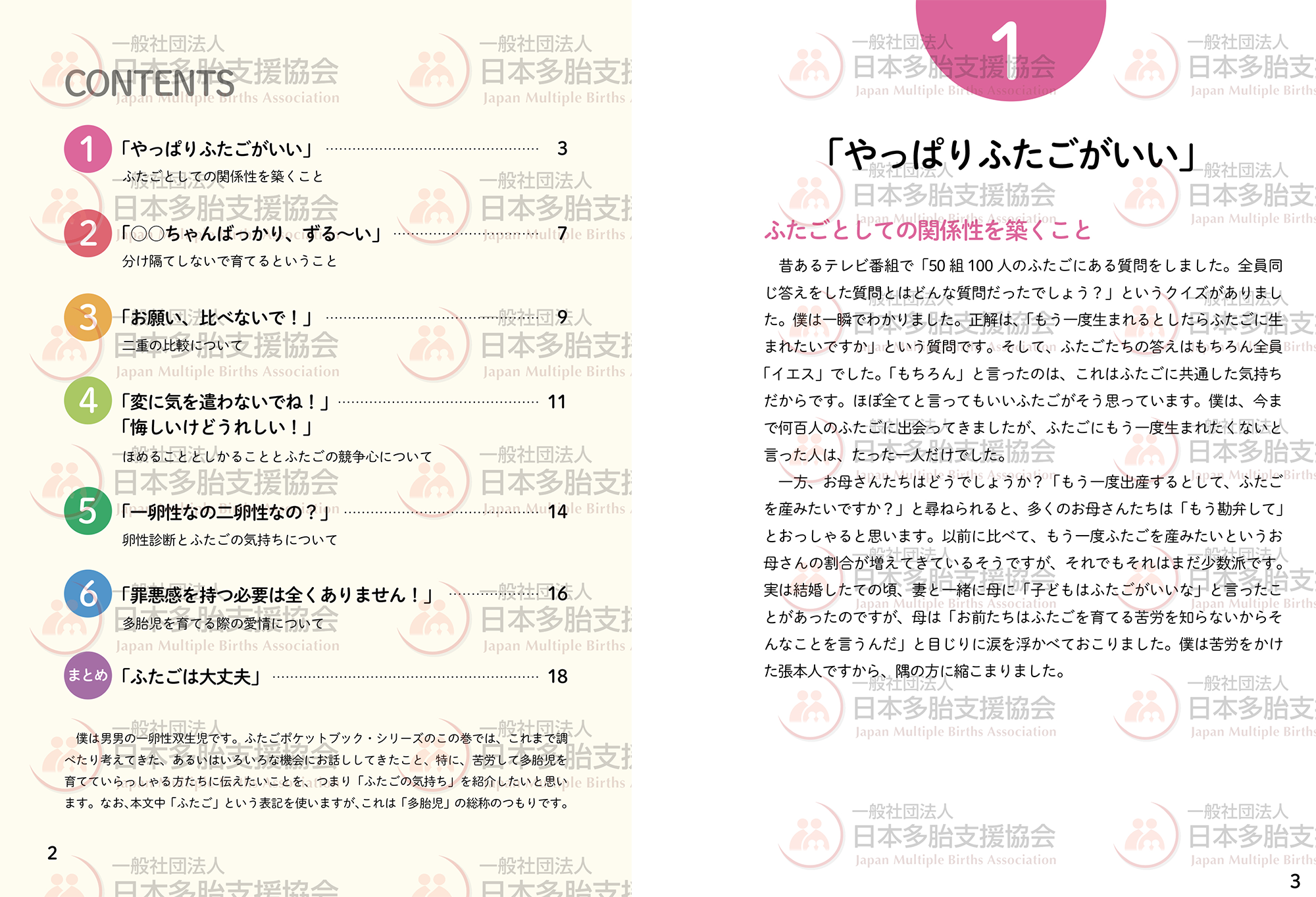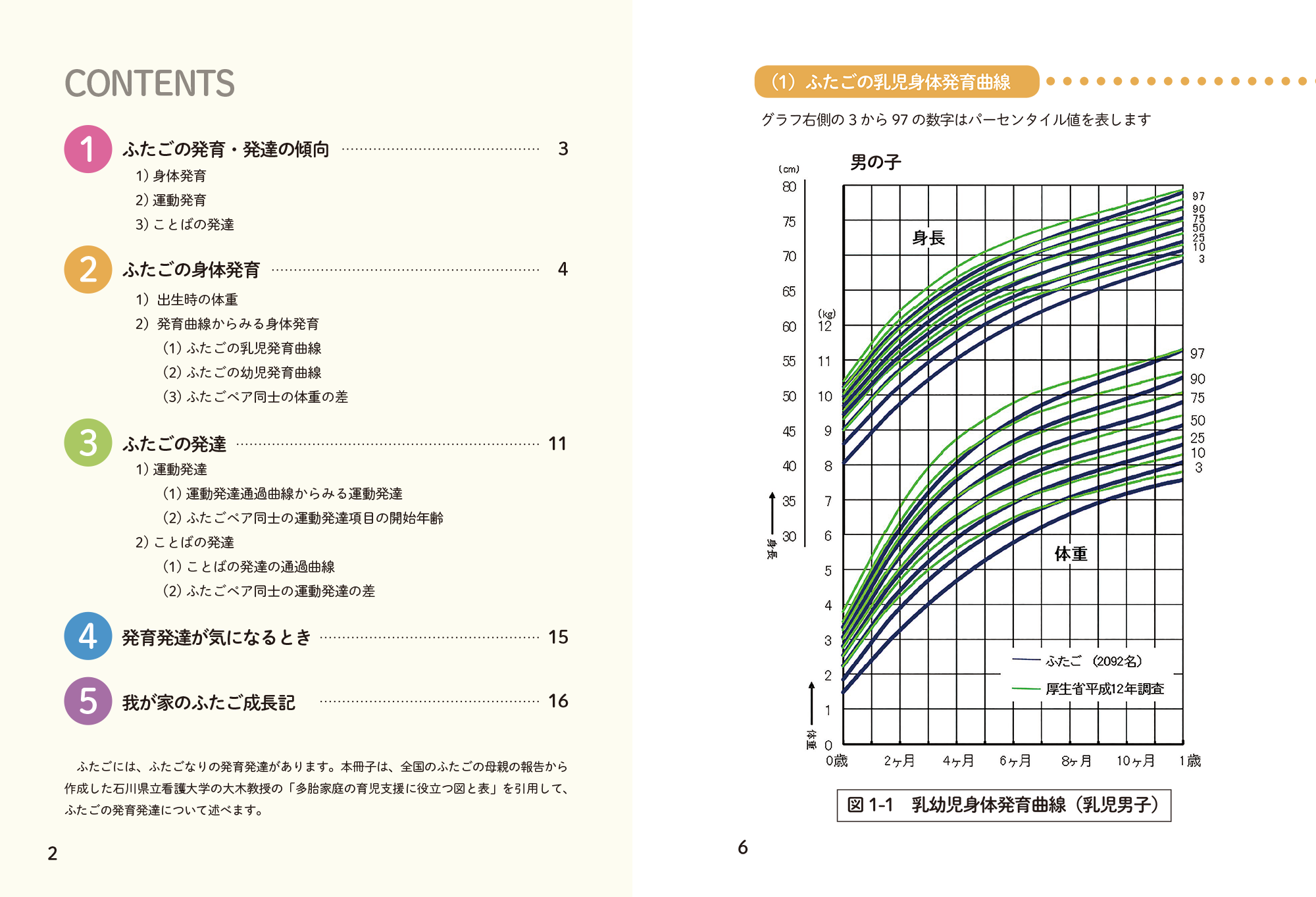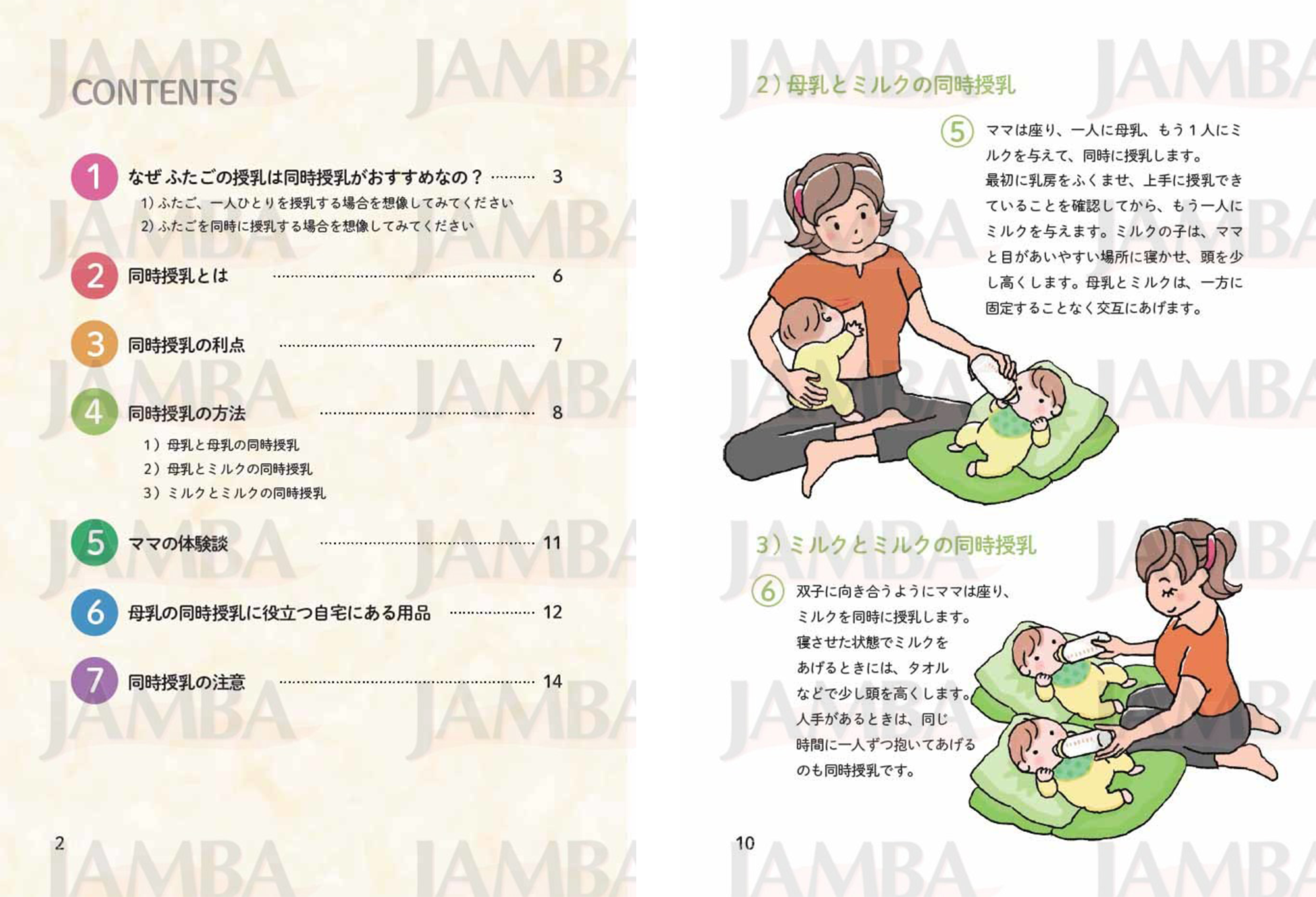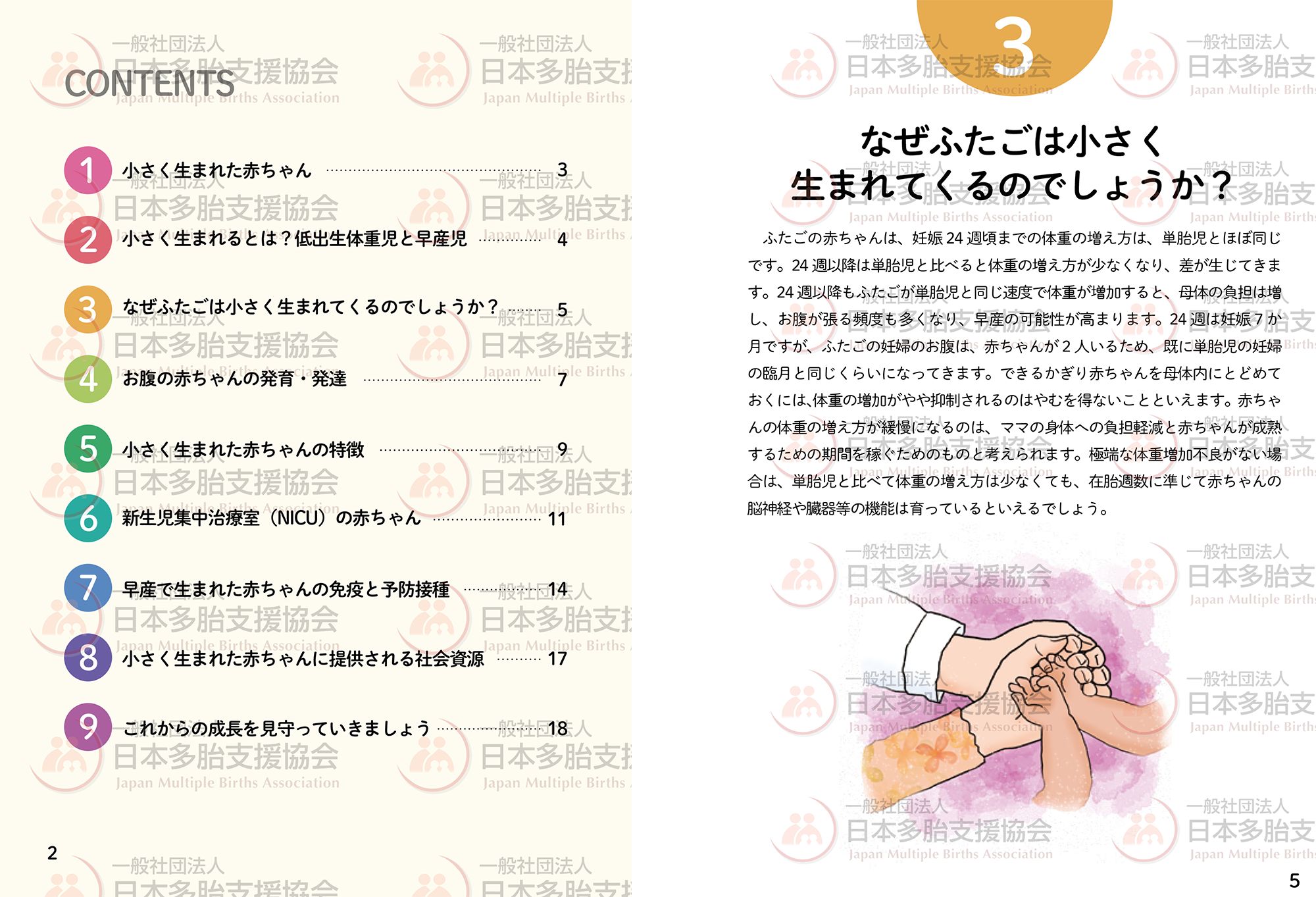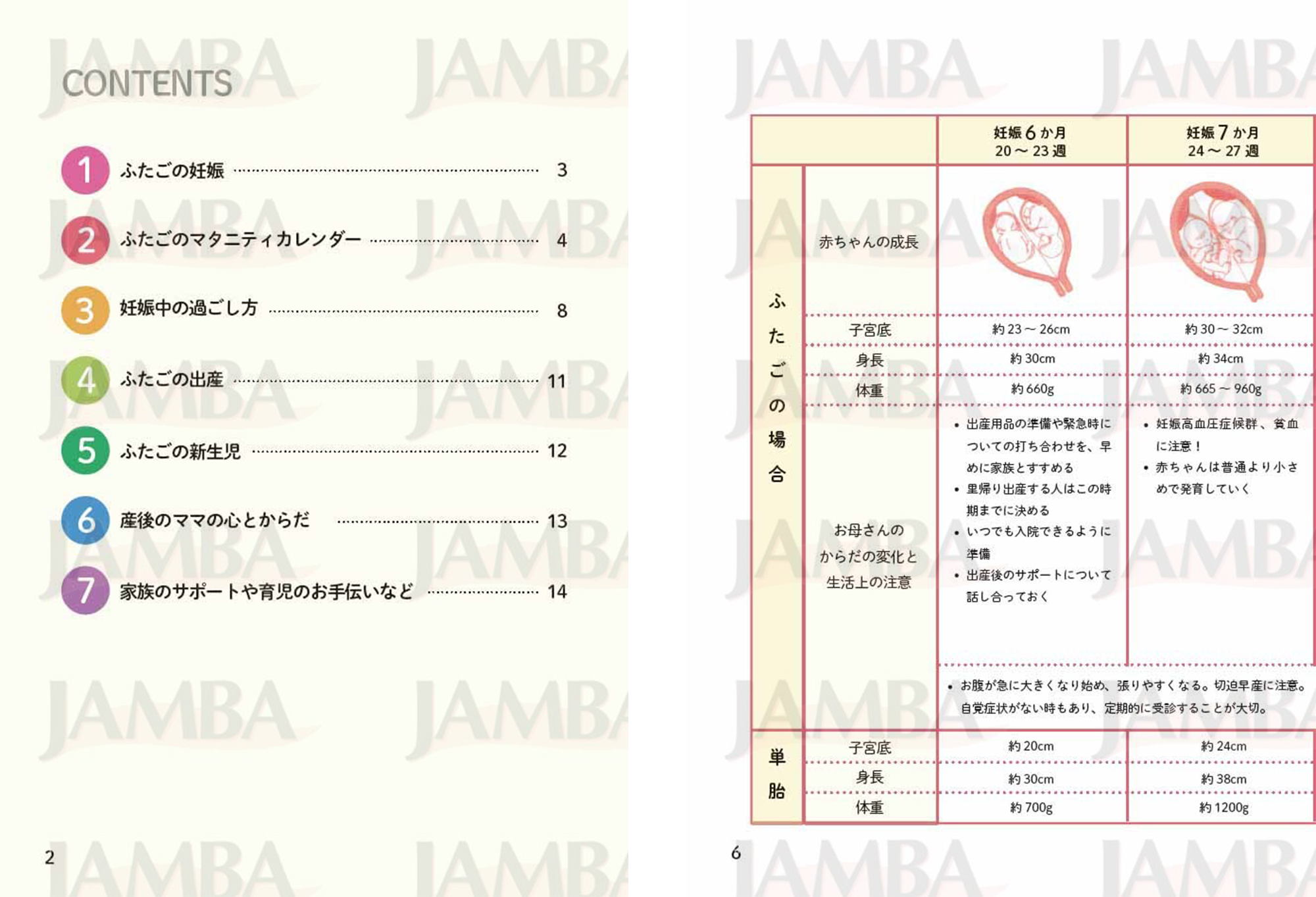2025年7月5日~6日大阪市立青少年センターKOKO PLAZAにて第1期「全国多胎支援者リーダー交流会」を開催しました。
参加者は、福井県(きらきらクラブ、きらきらツインズ)、富山県(tatai fam)、滋賀県(ツインクルザウルス、connnect to)、京都府(京都府助産師会えんどうまめの会)の皆さん、各地で多胎支援に尽力されている方々です。
今回、connect toさん、京都府助産師会の方々は全員が助産師の有資格者だった為、地域の方々と専門職チームに分けて実施しました。(専門職チームは専門職用の支援者ボトムアップシートを活用)
事前に日本多胎支援協会の理事が作った地域診断シート、多胎支援団体の発展チェックリスト(KPIシート)、支援者ボトムアップフローチャート(当事者用・専門職用)の3つの宿題に取り組んでの参加です。
研修初日は、志村恵代表理事の挨拶の後、参加者全員の自己紹介。今回多胎支援研修に対する熱い思いを語り合い、開始直後から熱気であふれていました。
講義1は、神戸女子大学服部律子教授による「多胎家庭への支援の必要性とピアサポーターの役割」。
以下のような内容のお話でした。
少子化で子どもの数は減っているのにもかかわらず、多胎の出生率は不妊治療の影響もあり上昇中。
しかし、残念ながら、多胎妊娠育児の理解はすすんでいないのが現状。要因としては、多胎に特化した保健指導や育児指導不足、ハイリスク妊娠の為、出産がゴールになりがちであること。産後の大変な時期は引きこもっていて、当事者の声をあげることができない等が考えられる。
「こども虐待による死亡事例等の検証結果」によると、多胎の第3次~19次までの心中以外の虐待死は25人(2.7%)、第20次報告では7人(7.1%)に上昇。低体重の第3次~19次では121人(13・2%)だったのが第20次報告では9人(16.1%)にまで上昇している。
次に多胎の妊娠、出産、育児の経験者に聞いた調査結果を紹介。多胎特有のストレスに対してどんな支援があると助かるか、どんな声掛けや保健指導が嬉しかったか等を具体的に紹介。
また同じように過酷な多胎育児を経験した先輩ママによるピアサポートの効果を説明。相談者は、わかってくれること、認められていること、自分は一人ではないと実感することができ、支援者自身もエンパワメントできると解説。
講義の最後には、妊娠期からの切れ目のない支援を目指して、当事者、専門職、地域住民が協働で多胎家庭をサポートしていくネットワークの構築こそが有効であると話され参加者は大きく頷いていました。
休憩時間を挟んで、講義2は、ぎふ多胎ネット理事長糸井川誠子さんから「命を救うために専門職・支援者ができること~ある虐待事件から学ぶ~」をテーマに学習。
実際にあった虐待事件をもとに、いつ、どこで、誰が、何をすれば虐待を防げたのかを考えました。
保護者がだす小さなSOSを見逃さないこと、あと一歩踏み込んだ支援があれば、誰かが気付いていれば助かる命があるということを肝に銘じて日々の支援活動に取り組む必要があると痛感しました。
また、ぎふ多胎ネットの妊娠期からの切れ目のない充実した多胎支援メニュー、ファミリー教室、病院サポート、家庭訪問、健診サポート、育児教室、多胎のつどい訪問、多胎イベント、多胎に関する研修会の開催、多胎支援に関する講師の派遣等を具体的に紹介。参加者もきめ細かい充実した支援メニューとその効果を学び自分の地域でもできそうなことから初めてみたいと感じていました。
2つの講義の後は、各地域、専門職グループに分かれて、地域診断シートを活用しながら、自分の地域の強みと弱みを検討。
最後に参加者全員で記念撮影をして1日目のプログラムを終了しました。
翌日は、朝9時より「今の私たち、これからの私たち」と題してグループワークを開始。
付箋紙も活用しながら、将来像(10年後の姿)、中間計画(3年後までにやりたいこと)、短期計画(今年度やりたいこと)、今年度の事業計画として、人材、場所、資金、その他の項目で実現のために必要なこと、どうやって獲得するか、タイムスケジュールを作成しました。
研修のクローズは、各グループの発表タイム。自分の地域の多胎支援の現状を把握しながら、それぞれ地域の特性、強みを活かした計画を熱く語りました。他のチームや日本多胎支援協会理事からも質問や更によい計画になる為の助言が飛び交い、活気に満ちた時間となりました。
研修の最後は、1人ずつ感想を発表。1日目のドキドキした様子とは違い、これから自分たちのフィールドに戻って新たな気持ちで多胎支援に取り組んでいきたいという様子が伝わりました。
多地域、多職種との交流を通じて、専門職、ピアそれぞれの考え方を改めて知ったことで、参加者の住む地域で多胎支援の輪が広がっていくことが確信できる研修会でした。日本中どこでも安心して多胎を妊娠、出産、育児できる世の中を目指してまずは、日本多胎支援協会メンバーもしっかり参加者に伴走していきます。
本事業は、NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンドの助成を受けて実施しました。